「快活CLUB」がジムに進出!?異業種参入の背景と狙いとは?
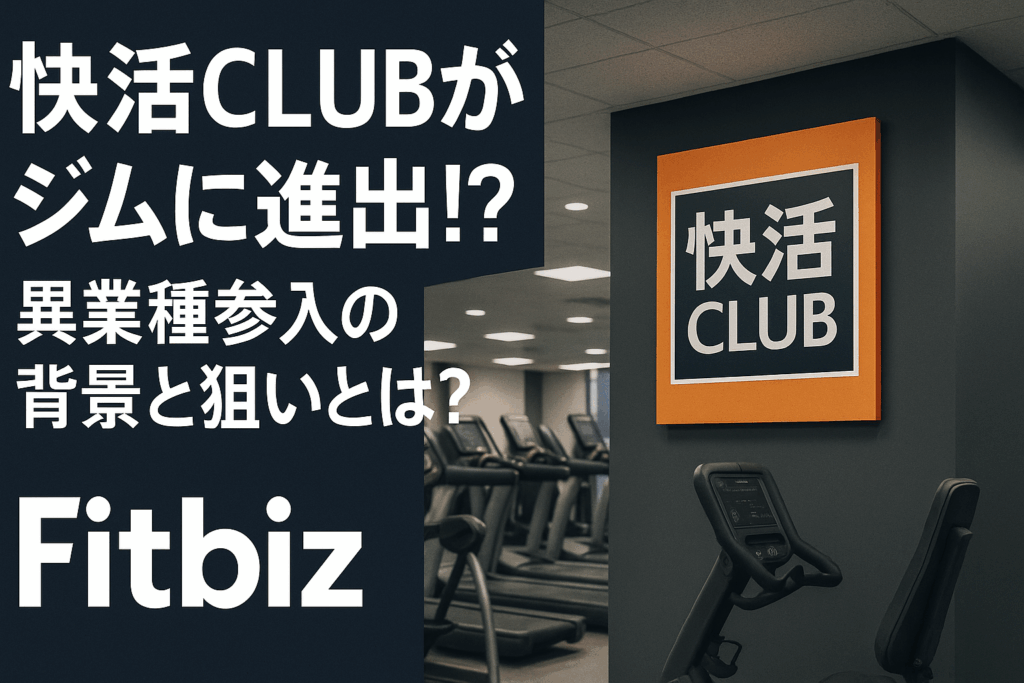
最近、インターネットカフェ大手の「快活CLUB」がフィットネス業界に参入したというニュースが話題を集めています。
しかもその新しいジムは「ソフトクリームが食べられる」など、これまでにないユニークなサービスを打ち出しています。
「なぜ今、ネットカフェがジムを始めるのか?」と疑問に思われる方も多いかもしれません。
背景には、フィットネス業界の“多様化”と“参入障壁の低下”があります。
従来のジム経営は大型店舗・人件費・設備投資といった高コスト構造がネックでしたが、今では無人運営や会員管理のDX化が進み、小規模でも成り立つビジネスモデルが確立しつつあります。
つまり、異業種でも比較的スムーズに参入できるようになっているのです。
加えて、「快活CLUB」はすでに24時間営業・会員管理・個室スペースといったインフラを持っており、
それを活かして“ちょっと運動もできる快適空間”として新たな価値を提案しようとしています。
従来のフィットネスの枠にとらわれない発想は、「運動が苦手」「ジムに通うのはハードルが高い」と感じる層にもアプローチできる強みがあります。
こうした動きは、今後のジム経営においても無視できません。
「運動×○○」という組み合わせで、ユーザーのライフスタイルに寄り添う柔軟なサービスが求められているのです。異業種参入の波は“脅威”でもあり、“気づき”のチャンスでもあります。
“ソフトクリームが食べられるジム”のユニーク戦略に注目!
「ジムなのにソフトクリームが無料で食べられる!?」――そんな一風変わったサービスを展開しているのが、快活CLUBが新たに立ち上げたジムです。通常なら「運動=健康的・ストイック」というイメージですが、この施設はあえてその常識を逆手に取っています。目的は、“運動が苦手な人でも気軽に足を運べる場所を作る”こと。
実は、ジムを敬遠する人の多くが「雰囲気が硬い」「運動が続かない」「そもそも入りづらい」といった心理的なハードルを感じています。そこで、快活CLUBは“ゆるいジム”というコンセプトで、「まずは楽しむ」「来たくなる空間を提供する」という点に注力しました。
このような戦略は「エンタメ型フィットネス」とも呼ばれ、近年注目されているマーケットです。例を挙げると、カフェ併設型のジムや、アニメ・ゲームとのコラボ施設などもその一種です。健康志向が高まりつつも、“義務感”ではなく“楽しさ”を求める傾向が強まっており、そうしたニーズにマッチしています。
もちろん、ソフトクリームは単なる“話題づくり”ではなく、リラックスやご褒美的な要素として機能しています。あえて糖質を否定せず、バランスの良いライフスタイルを提案している点もユニークです。
中小ジムにとっても学べるのは、「ジムの役割は運動だけではない」という視点です。空間や体験そのものが“価値”になり得る時代、ちょっとした遊び心が集客のヒントになるかもしれません。
なぜ今、フィットネス業界に新規参入が相次ぐのか?
ここ数年、フィットネス業界には異業種からの参入が相次いでいます。快活CLUBのようなインターネットカフェをはじめ、家電量販店、コンビニ系ジム、さらには不動産・ホテル業など、これまで運動とは縁遠かった企業までもがジムビジネスに乗り出しているのです。
その背景には、大きく3つの流れがあります。
まず1つ目は、「市場の裾野が広がったこと」。以前は筋トレ愛好家や健康志向の高い人が中心だったフィットネス市場が、今や“誰でも通えるライト層向け”へと拡大しています。特にchocoZAPやエニタイムのような「低価格・簡単・24時間型」のジムが成功したことで、ビジネスモデルとしての収益性と持続性に注目が集まるようになりました。
2つ目は、「テクノロジーの進化」。会員管理や予約システム、鍵付きの入退室管理、監視カメラによる安全対策など、ITやDXの導入により、少人数でも運営可能な“スマートジム”の普及が進んでいます。これにより、初期投資を抑えつつも安定した運営ができるようになり、参入障壁がぐっと下がりました。
そして3つ目は、「業界全体の回復と成長期待」。コロナ禍で一時は打撃を受けたフィットネス業界ですが、2024年以降は市場規模が急回復し、今後も拡大が見込まれています。帝国データバンクの調査では、2025年の国内市場は約7,000億円規模に達するとの予測もあり、成長産業としての期待が高まっています。
こうした追い風の中で、異業種企業が持つ「独自の強み」——たとえば“滞在性の高さ”“多目的空間”“ブランド力”など——を活かし、独自色のあるジムサービスを打ち出しているのです。
中小ジムがとるべき対応策は?顧客の“期待のズレ”を埋めよう
快活CLUBのような異業種によるフィットネス参入が進む中、中小規模のジムやパーソナルジムは「どう対応すればよいのか?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、こうした変化の波は“脅威”であると同時に、“改善のヒント”でもあります。
今の消費者は、「ただ痩せたい」「筋肉をつけたい」だけではなく、「楽しく続けたい」「ストレスなく通いたい」といった心理的なニーズも求めています。つまり、“効果”だけではなく“体験”そのものが選ばれる時代になってきているのです。
この中で特に重要なのが、「ジム側の提供価値」と「お客様の期待」との“ズレ”をいかに埋めるかという視点です。たとえば、ジム側は「結果にコミット!」を全面に押し出していても、お客様は「まずは週1で気軽に運動したい」程度の動機で来店するかもしれません。このズレを放置すると、満足度が下がり、退会率が上がる原因になります。
では、どうすればよいのでしょうか?
中小ジムが実践できる対応策として、以下の3つが挙げられます。
- “顧客インタビュー”の実施
→ 現在の会員がなぜ通っているのか、どう感じているのかを把握しましょう。 - “選ばれる理由”の明確化
→ 価格・立地・指導力・雰囲気など、自店の強みを言語化してアピール。 - “体験価値”の強化
→ ちょっとしたアメニティやLINEでの応援メッセージなど、小さな心配りがリピートにつながります。
大手の戦略をそのまま真似るのではなく、自店に合った“小さな変化”を積み重ねることが、地域で生き残るジム運営の鍵になります。
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。